「出金できない」「追加の税金や清算費を支払えば返金と言われた」──暗号資産まわりの相談が急増しています。
本記事では仮想通貨詐欺の調査会社に依頼する前に知っておくべき基礎知識を、専門的な視点でわかりやすく整理。調査の流れ・費用相場・選び方のチェックリスト・返金の可能性と限界・リカバリースキャムの見分け方までを一気に学べます。初動での情報整理が、その後の被害回復の可能性を左右します。
1. 仮想通貨詐欺の調査会社とは
仮想通貨詐欺の調査会社は、暗号資産に関する不正・トラブルについて技術調査(ブロックチェーン解析)と情報整理を行う民間事業者です。主な役割は以下のとおり。
- 資金トレース(On-chain):送金アドレス/TXIDから資金の流れを可視化
- 関係者・サイトの関連性分析:OSINTで運営・関与アカウントを推定
- 証拠保全:スクリーンショットやログの保全方針、ハッシュ化、タイムスタンプ
- 報告書の作成:警察・弁護士・金融機関・交換業者への照会下地となる資料化
- 通報・照会の支援:どこに、何を、どの順で出すと通りやすいかの設計
ポイント
調査会社は「返金を保証する場所」ではありません。事実の可視化とルート設計が本来業務で、返金可否は相手の資金移動・管轄・協力先に依存します。
2. 依頼すべきケース/自力で動けるケース
依頼すべきケース
- 送金先が多数のアドレスへ分岐・集約され、自力で追い切れない
- 相手とやり取りが外部チャットのみ(Telegram/WhatsAppなど)、関与サイトが多数
- 複数名の被害が見込まれ、共同での照会・報告が必要
- 海外事業者が絡み、照会先や文面の作り方が不明
- 証拠保全を訴訟や刑事・行政へ引き継ぐ可能性がある
自力で動けるケース
- TXIDやアドレスが明確で、単純な一往復送金のみ
- 送金先が大手取引所の入金アドレスで、本人名義の口座への誤送金など
- 事業者のサポートに公式フォームがあり、必要情報を用意できる場合
3. 調査会社が行う主な調査手法
3-1 On-chain解析(ブロックチェーン調査)
- アドレス/TXIDの追跡:資金の入出金、スプリット、タンブリングの痕跡
- タグ情報の参照:既知の交換所・サービス・ブリッジ等への流入/流出
- タイムライン化:要求メッセージと送金タイミングの相関を整理
3-2 OSINT(オープンソース情報調査)
- ドメイン・SSL・WHOIS・ホスティングの関連性
- SNS・チャットアカウントの使い回し、画像のリバースサーチ
- 会社情報・特商表記・規約の矛盾やテンプレ使い回しの検出
3-3 DFIR(デジタル・フォレンジック)
- 端末・ブラウザのキャッシュ/ログからアクセス痕跡を抽出
- リモート操作ツール(AnyDesk等)の接続履歴
- メールヘッダ・IP・時刻同期の整合性確認
3-4 関係機関との照会支援
- 交換所・ウォレット事業者への事実照会
- 金融機関・決済事業者へのチャージバック可否確認
- ドメイン・ホスティングへの利用実態照会
4. 調査の標準プロセス(初動~報告書)
- ヒアリング&スコーピング:被害経緯・送金情報・連絡手段・関与URLを収集
- 証拠保全:スクショのルール、ファイル命名、改ざん防止(ハッシュ・タイムスタンプ)
- 一次調査(On-chain+OSINT):取引の脈と関与主体の候補を整理
- 中間共有:不足情報の洗い出し、照会先の優先順位決定
- 二次調査:必要に応じDFIRや追加OSINT、複数被害の統合
- 報告書:時系列・金額・アドレス・URLの一覧/相関図/推奨アクション
- フォロー:照会文面・提出先・提出順のガイド、進展に伴う追補
成果は「返金」ではなく、**“どこに何を出せば前に進むかが明確になる状態”**です。
5. 調査会社の選び方:比較ポイントと質問集
比較ポイント(最低限)
- On-chainの経験値:主要チェーン(BTC/ETH/TRON/BSC など)での実績
- 報告書の質:図解・相関図・時系列・証拠リンクの再現性
- 法的連携:弁護士や公的機関との連携経験、照会文面の型を持つか
- コンプライアンス:守秘義務・個人情報保護・ログ取り扱いのポリシー
- 費用の透明性:見積の内訳、追加費の発生条件、成果物の範囲が明確か
依頼前に投げるべき質問例
- **「一次調査の範囲」と「報告書のサンプル」**を見せてもらえますか?
- 似たパターンの調査実績は?(高配当ダッシュボード型/ロマンス誘導型など)
- 想定期間とマイルストーンは?(中間共有の頻度)
- 照会先の優先順位は? それぞれの期待値は?
- 追加費用が出るケース(例:DFIRや大量アドレス解析)の条件は?
6. 費用相場・課金形態・見積もりの読み方
- 一次調査(短期):数万円~20万円台が目安
- 本調査(複数ルート・深掘り):30~100万円前後
- 大型案件/複数被害統合:100万円以上も(期間・要求精度に依存)
課金形態は「固定」「時間(Time & Material)」「着手+成功報酬」のいずれか。
成功報酬型は魅力的に見えますが、成功定義(例:交換所のフラグ付け・資金動向の把握・返金実行など)を明確に。“返金額の◯%”のみで契約しないのが安全です。
7. 調査期間と成果物(KPI/アウトプット)
- 期間の目安:一次調査 1~2週間/本調査 2~8週間
- 成果物:
- 時系列表(日時・金額・通貨・ネットワーク・TXID)
- 資金フロー図(ノード/エッジで可視化)
- 関与URL/アカウント一覧(証拠リンク付き)
- 推奨アクション(提出先・文面・順序)
KPIは「返金可否」ではなく、照会の受理・フラグ付け・資金動向の可視化・再発防止。過度な“成果保証”をうたう業者は避けましょう。
8. 法的連携と照会:弁護士・警察・取引所・事業者
- 弁護士:刑事・民事の戦略設計、仮差押え・送達・国際間手続き
- 警察・公的機関:被害届・相談受理。報告書形式により通りやすさが変わる
- 交換所・ウォレット運営:フラグ付け/社内照会(事実ベースの資料が必須)
- 金融機関・決済事業者:チャージバックや口座調査の可否確認
アクションは順序が重要。先に資金の動向を可視化し、関係各所に通る資料を作るのが近道です。
9. 返金の可能性と限界:誇大広告に注意
- 返金は“可能性”の問題:相手の資金がどこに留まっているか(交換所・ブリッジ・新規アドレス)で変動
- 海外管轄・匿名性の高いチェーンでは難易度が上がる
- 成功事例は存在するが、事案の個別事情に強く依存
- 「100%返金保証」「税金を払えば出金」などの文言は要注意ワード
10. 二次被害「リカバリースキャム」を見分ける
被害者を探して近づく返金代行詐欺が横行。以下に当てはまる場合は要注意。
- 先に大きな成功報酬や着手金を要求
- 個人ウォレットへの送金を指示
- 「公的機関と連携済み」「徹底返金」など断定的表現
- 匿名SNSのみでの連絡、契約書なし
- 事例や報告書の再現性を示さない
11. 依頼前に準備する証跡チェックリスト
★は重要度高。スクショ+テキスト控えで二重保存。
- ★ 送金情報:TXID/送金元・先アドレス/金額/通貨/ネットワーク
- ★ 関与URL:LP/ログイン/入金/規約/会社情報(各ページのスクショとURL)
- ★ 連絡履歴:チャット・メール・DMの原文(日付・時刻入り)
- アカウント情報:取引所・ウォレットの登録メール(PWは残さない)
- 支払い証跡:銀行・カード明細の該当部分
- 端末情報:インストールさせられたアプリ、リモートツールの接続履歴
- 時系列メモ:いつ/どこで/誰に/何を言われたか
テンプレ
送金日時:/金額:/通貨・ネットワーク:
送金元:/送金先:/TXID:
関与URL:/連絡先ID:/要求内容(原文):
追加メモ(スクショのファイル名・取得日時など):
12. よくある質問(FAQ)
Q1. いまからでも間に合いますか?
A. 可能性は事案次第。まず現時点の痕跡を確実に残し、資金の動向を可視化しましょう。
Q2. どのくらいの期間で結果が出ますか?
A. 一次調査は1~2週間が目安。本調査・照会は数週間~数か月に及ぶこともあります。
Q3. 調査費用は取り戻せますか?
A. 調査費用は被害回復の可能性を上げるための投資であり、返金保証の対象ではありません。費用対効果は事案の規模・難易度で検討します。
Q4. 情報を渡すのが不安です
A. 守秘義務・個人情報の取り扱いを書面で確認しましょう。ログの保存方法や報告書の開示範囲も事前合意が大切です。
13. まとめ:まずは“触らず、残す”
- 追加入金は停止
- 証跡を整理(TXID・アドレス・URL・原文ログ・時系列)
- 事実ベースの資料化 → 関係各所へ適切な順番で照会
- 調査会社を使う目的は「返金保証」ではなく、可視化と再現性の高い資料で次の一手を作ること
迷ったら、アカウントを慌てて削除せず、いまの状態を記録してください。
初動の“質”が、その後の被害回復の可能性を大きく左右します。

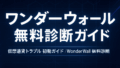
コメント